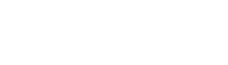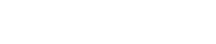匂いが分からない原因は風邪?コロナ?ストレス?
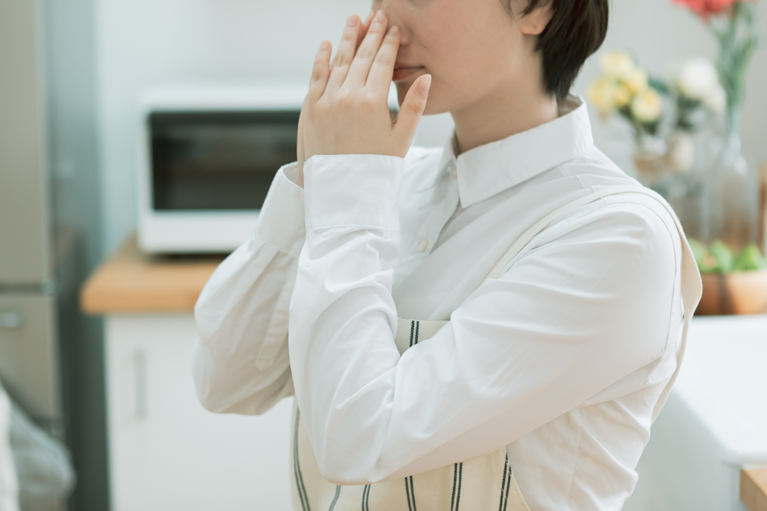 匂いが分からない場合は、様々な原因が考えられます。副鼻腔炎、新型コロナウイルス感染症、感冒症状による鼻づまり、脳細胞や脳神経の障害などが関わっており、医師の問診と検査を受け、原因を特定する必要があります。匂いのことでお困りの際は、大阪市浪速区にある大阪なんばJUN耳鼻咽喉科へお気軽にご相談ください。
匂いが分からない場合は、様々な原因が考えられます。副鼻腔炎、新型コロナウイルス感染症、感冒症状による鼻づまり、脳細胞や脳神経の障害などが関わっており、医師の問診と検査を受け、原因を特定する必要があります。匂いのことでお困りの際は、大阪市浪速区にある大阪なんばJUN耳鼻咽喉科へお気軽にご相談ください。
匂いを正常に感じられなくなる嗅覚障害とは
嗅覚障害とは、匂いを認識できなくなる、あるいは、匂いを正常に感じられなくなる病気です。
通常は、匂いを感じる次の3つのステップが機能しています。
Step.1 鼻腔内の嗅粘膜で匂いをキャッチする
Step.2 匂いが嗅神経を介して脳に伝わる
Step.3 大脳で匂い情報を分析・処理する
つまり嗅覚障害とは、この3つのステップのいずれかに障害が発生している状態と言えます。嗅覚障害は、匂いを感じる量が減る「量的嗅覚障害」と、匂いの感じ方が変化する「質的嗅覚障害」に分類されます。
【量的】嗅覚障害
匂いを感じる量によって、以下の種類に分けられます。
- 嗅覚低下…匂いを感じる量が減る状態
- 嗅覚脱失…匂いをまったく感じない状態
当院へ嗅覚の悩みで受診される患者様は、この量的嗅覚障害であることが多いです。
【質的】嗅覚障害
匂いを感じる能力に異常を来してしまった状態を質的嗅覚異常と言います。匂いの感じ方によって、以下のように分類されます。
- 刺激性異嗅症…正常な匂いとは異なる匂いとして感じる状態
- 自発性異嗅症…なにも匂い物質は存在しない環境で匂いを感じる状態
他に、特定の匂いのみが感じ取れなくなる嗅盲(きゅうもう)も含まれます。
嗅覚障害の主な症状
 嗅覚障害になると以下のような症状が現れます。
嗅覚障害になると以下のような症状が現れます。
- 匂いが分からない
- 何を嗅いでも同じ匂いがする
- 馴染みの食べ物なのに違う匂いがする
- 食事が美味しく感じられない
- 飲み物の匂いがしない
食事や飲み物の味わいが損なわれるため、味覚は正常でも食欲が下がってしまい、二次的に体重が減少する方もいます。
嗅覚障害の3種類とその原因
①鼻づまりや鼻通りが悪くなって
起こる「気導性嗅覚障害」
鼻腔内の物理的な閉塞・狭窄によって、匂いが嗅粘膜までたどり着かないことで生じる嗅覚障害です。この場合は、鼻腔の閉塞や狭窄を治療することで、嗅覚の改善が見込めます。
症状
鼻腔の閉塞や狭窄の原因となっている多量の鼻水や、鼻づまりなどの症状が現れます。
原因
主に慢性副鼻腔炎・鼻中隔湾曲症・アレルギー性鼻炎などが原因疾患です。稀に、鼻の骨折によって骨が湾曲して発症する例もあります。
②嗅神経の異常によって起こる
「嗅神経性嗅覚障害」
匂いを感じ取ることはできても、嗅神経が障害されており、匂いの伝達ができなくなる嗅覚障害です。神経障害の治療は長期間かかるため、その間に後遺症が残ってしまうことがあります。後遺症を最小限にとどめるためには、早めの治療開始が望ましいです。
症状
匂いが感じられなくなること以外に、実際の匂いを異なる匂いとして感じることが特徴的な症状です。またウイルス感染後に発症する場合があり、その際は発熱やだるさなどの風邪症状も伴います。
原因
主にウイルス感染や内服薬などの薬物によって嗅神経が障害されてしまうことが原因です。新型コロナウイルス感染症が流行した際は、嗅覚障害を発症する患者様が多くいらっしゃいましたが、嗅神経性であったと考えられています。他には、事故や手術などで嗅神経が傷つくこともあります。
③匂い処理に対して脳に異常が
起こる「中枢性嗅覚障害」
脳組織や脳神経に問題が生じている際に、匂いの情報が脳に伝わらない、また、脳で処理できないために生じる嗅覚障害です。
症状
鼻づまりや鼻水といった症状は伴わず、嗅覚の損失のみであることが多いです。しかし中には、アルツハイマー型認知症の初期症状として現れることがあり、その場合は認知機能の低下も見受けられます。
原因
主な原因は転倒や外傷による頭部外傷、また脳腫瘍・パーキンソン病が挙げられます。
コロナウイルス感染後の嗅覚異常
コロナウイルス感染症後の後遺症として、嗅覚障害を発症するケースは多く報告されています。感染症が治癒した後、数週間以上が経って嗅覚が回復する例もありますが、永続的な後遺症になる可能性もあります。
嗅覚障害の検査
嗅覚障害の原因特定のため、問診をはじめ複数の検査を行います。
検査
問診
 患者様の主観情報は、原因特定に重要なヒントです。そのため問診では、いつから嗅覚の異変があるか、どのようなものの匂いを感じないか、その他の感冒症状の有無、周囲やご自身が感染症に罹っているか等をおうかがいします。
患者様の主観情報は、原因特定に重要なヒントです。そのため問診では、いつから嗅覚の異変があるか、どのようなものの匂いを感じないか、その他の感冒症状の有無、周囲やご自身が感染症に罹っているか等をおうかがいします。
前鼻鏡検査・内視鏡検査
 この検査は、小さなカメラ(ファイバースコープ)を鼻腔内に挿入し、鼻粘膜の炎症や腫れの程度を判断するために行います。主に気導性嗅覚障害の診断で使用します。
この検査は、小さなカメラ(ファイバースコープ)を鼻腔内に挿入し、鼻粘膜の炎症や腫れの程度を判断するために行います。主に気導性嗅覚障害の診断で使用します。
嗅覚障害の治療
嗅覚障害の治療は、原因や種類に沿って複数の方法から選び行います。一般的な方法として、鼻洗浄、ネブライザー療法、抗生剤内服などの薬物療法がありますが、当院では以下の治療法を取り入れております。
ステロイド点鼻療法
 鼻の通りを改善させたい場合や、嗅神経障害を軽減する場合に、ステロイド点鼻薬を使用します。この薬は、目薬のような仕組みで、鼻に直接滴下する方法で投与します。投与の際は、薬剤を鼻の奥まで届けるために、鼻の穴が天井を向いた姿勢を作ることがポイントです。
鼻の通りを改善させたい場合や、嗅神経障害を軽減する場合に、ステロイド点鼻薬を使用します。この薬は、目薬のような仕組みで、鼻に直接滴下する方法で投与します。投与の際は、薬剤を鼻の奥まで届けるために、鼻の穴が天井を向いた姿勢を作ることがポイントです。
なお、ステロイドの副作用症状の有無を観察しながら治療を進めますのでご安心ください。
漢方薬
他の治療法と組み合わせられる薬剤として、当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)という漢方薬を使用することがあります。嗅細胞の再生を活性化させる効果があり、嗅覚障害の改善を助けます。
亜鉛を摂取
亜鉛は嗅細胞の生成に必要な成分ですので、亜鉛が適切に補充されると嗅細胞の新陳代謝が正常に行われ、嗅覚障害の進行予防や改善促進になります。
定期的な採血にて亜鉛の血中濃度を測定し、最適な摂取方法や適量をご案内します。